
こんにちは。ウマ子です!
ウマ子ってどんな人??
・保育士歴15年の元保育士
・主任兼新人保育士教育担当経験あり
・子育て中の二児のママ
・現在子育て専念中
今回の記事では、子どもの噛み付きについてお話します。
こんな人にオススメの記事
◯子どもの噛み付きに困っている
◯子どもの噛み付きの原因や対処法について知りたい

子どもの噛み付きについて悩んでいませんか??
子どもの噛み付き癖がひどい…
友だちに噛みつかれてしまった…
クラスで噛み付きが流行してしまっている…
などと、噛み付きに関する悩みも多いかと思います。

ウマ子はこれまで、噛み付きが見られやすい1.2歳児クラスの担任を複数回行ってきました。そのような経験を元に今回の記事では、子どもの噛み付きについて、具体的にお話をしたいと思います。
噛み付きでお困りの保育士さんやママパパさんの参考になると嬉しいです!!
子どもの噛み付きって?

何で子どもって噛むの?
噛むって普通の行動じゃないよね?
よくあることなの?
こんな風に感じる方も多いかもしれません。
子どもに関わる職業をしているとわかりますが、
結論から言うと子どもの噛み付きは非常によくあることです。

子どもが噛む理由を詳しく説明していきます!
子どもは産まれたての赤ちゃんの頃は、楽しい、悲しい、嬉しいなどの感情はなく、「快」「不快」のみのシンプルな感情のみしかないと言われています。
そこからだんだんと成長と共に、様々な感情が芽生えてくるようになります。
1歳頃から自我が芽生えていろんな感情が出てくるようになり、1歳半頃から特に自分の気持ちを喃語や簡単な言葉、身振りなどで伝えるようになります。
「楽しい」「嬉しい」という感情と合わせて、「いやだ」「思い通りにいかなくて悔しい」などマイナスの感情も出てくるようになります。

いわゆるイヤイヤ期の入り口ですね。
噛み付きをするようになった=成長の証でもあります。
この頃の子どもは、まだ自分の気持ちを言葉にして相手に伝えるという事はできません。
自分のしたい事や気持ちは明確に出てきているのに、それをスムーズに相手に伝える方法がわからない、といった状況です。
そのため、自分の気持ちを大人や周りの人に伝えようと、かんしゃくを起こしたり、相手に噛み付いたりという行動につながります。
噛み付きの原因

噛み付きの原因は大きく分けて3種類あります。
理由なき噛み付き

そこに噛むものがあったから。つまり理由がなく、噛んでみたかったから噛んでみた、という噛み付きです。
これは、0.1歳児の低年齢の子どもに多く、保育園で子ども同士の距離が近い時に起こりやすいです。
面白いもので子どもは不思議と穴に興味を示します。
0.1歳児ですと、まだ自分の耳や鼻などの穴の存在に気付かず、自分の耳や鼻よりも友だちの方が見えやすいので、友だちの口に指を入れてしまう、入れられた子どもは反射で噛んでしまう、という事も珍しくありません。
反対に、歯の生え始めで、なんとなく歯茎がむずがゆくて、近くにあったお友だちの腕を噛んでしまう、という事もあります。
別の方法で欲求を満たしてあげましょう!
友だちの口や耳に指を入れたがる子どもの場合は、指先を使って遊べるようなおもちゃのリモコンやシリコンプチプチなどを使用して、遊びにつなげるようにします。
なんでもとにかく噛みたい子どもの場合は、歯固めや噛んでも良い布製のおもちゃなどを使用して、遊びにつなげるようにしていきます。
強い口調で一方的に叱ることはNG!
この場合は、噛む事はいけない事だと認識していない場合がほとんどなので、一方的に強い口調で叱ってしまうと、何がいけないのかを子どもが理解しないまま、恐怖心だけ与えてしまう事になります。
その為、落ち着いた口調で「痛いよ、しないでね」などと短い言葉でわかりやすく伝えた上で、おもちゃを渡して子どもの欲求を満たせるように関わっていきましょう。
自分の気持ちを相手に伝えるための表現方法

自分の気持ちを相手に伝えるための表現方法としての噛み付き
自我の芽生えにより自分の気持ちが明確に出てきて、それに対してうまくいかない気持ちとして、噛み付く事があります。
自分の気持ちは明確に出てきたけれど、相手に言葉にして伝えるという事が咄嗟に出来ないときに見られる行動です。
2.3歳の子どもに多く見られます。
集団ならではの姿でもあるので、保育園で噛み付き癖がある子どもでも、家では全く見られない、ということは当たり前のようにあります。
言葉で自分の気持ちを伝える方法を示しましょう
大人の言葉をある程度理解できる年齢であるため、まずは子どもの気持ちを受け止めて言葉で代弁します。その後噛むことはいけない事だと伝え、別の方法で自分の気持ちを伝えられるよう示していきます。
例えば・・・
おもちゃの取り合いをして友だちを噛み付いてしまった場合
「おもちゃがとられそうになって嫌だったんだよね、嫌だったね」
「でも噛んだらお友だちが痛いから、いけないよ。
今度からは『やめて』ってお口で言うんだよ」
と分かりやすくできるだけ簡単な言葉で伝えます。一度伝えただけでは身に付かないため、噛み付こうとした場面を見逃さずに止めて、繰り返し伝えていきます。
一方的に噛んだことを叱ったり、噛み返したりはNG!
噛んだ理由を聞かなかったり、一方的に噛んだことだけ叱ると、子どもの理解につながりません。また、理解をしたとしても、自分の気持ちをわかってくれないもどかしさを感じるため、噛み付きがさらに激しくなってしまうこともあります。
また、痛みをわかってもらうために、「家で噛み返した方が良いですか?」と質問される方も時々いますが、噛み返してしまうと、「やってもいい行動なんだ」と認識してしまう可能性があるため、ご家庭であっても子どもに対して噛み返すことは避けましょう。
甘えたい気持ちの表れ

気持ちが満たされないことへのもどかしさ、甘えたい気持ちの表れの噛み付き
理由なく噛むことと少し似ていて、こちらの場合も噛むことが悪いことだとはあまり認識していません。
1歳前後に起こりやすく、慣れている保育士やパパママに噛むことが多く、甘えたい気持ちや遊んでいるつもりで噛むことがあります。
わかりやすい言葉で噛むことはいけないことだと伝えましょう
噛むことはいけないこと、相手が痛いことを伝える必要があります。
わかりやすい言葉や表情で「ここ痛いよ、やめてね」と伝えましょう。
その後、甘えたい気持ちや遊びたい気持ちを受容し、スキンシップ遊びなどをして、子どもの欲求を受け止めます。
甘えだから・痛くないから、と思ってスルーしたり遊んだりはNG!
噛むことが悪いことだと分かっていないため、激しく叱る必要はありませんが、いけないことだと伝える必要はあります。
甘噛みであっても、何かのタイミングで強く噛むようになることはありますし、スルーしたり遊んでしまうと、噛むという行動がその子どもの遊びのレパートリーに加わってしまいます。
保育園で噛み付きが起こったときの対処法

では、保育園で噛み付きが起きた場合にどのように対応しているのでしょうか??
具体的な対応方法についてお話しします。保育園によって対応は異なりますので、一例としてお話します。
必要な処置

もし噛み付きが起こった場合には、まず流水で流して噛み跡の状態を確認します。
赤く歯形に内出血の痕が残る、などの外傷がある場合は、冷やすと良いとされています。
ですが、保育園によって対応は異なりますので、看護師や園長、園医の指示に従うようにしましょう。もし、出血があったり大きくあざになってしまっている場合は、速やかに保育園の看護師や園医に相談しましょう。
大切な子どもを預かっている以上、保育園内の怪我や事故は保育園の責任です。保護者の方がお迎えに来た際に、いきなりパックリと赤くついた噛み跡をみると、衝撃も大きいかと思います。
その為、保育園によってその後の対応は異なりますが、噛みつかれた子どもの保護者に対して、お電話をして、状況説明と謝罪をすることが望ましいです。
子どもの噛み付きによって、裁判にまで発展する事例も過去にあったようです。わざわざお電話をする保育園は少ないかと思うのですが、保護者同士のトラブルを防ぐためにも、もし可能であれば、噛み付きが起きて噛み跡がハッキリと残っている場合は、保護者の方にご連絡をすると印象が大きく変わります。
噛んだ子どもへの対応

0.1歳の低年齢児の子どもが噛んだ場合は、短い言葉で、「痛いよ。ブッブーだよ。」などと噛んだのはいけないということを伝えます。
一度で理解することは難しいため、噛みつこうとする様子が見られた場合には素早く止めた上で、繰り返しわかりやすく言葉や表情で伝えていきます。
2.3歳以上の子どもが噛み付くときは、ほとんどの場合は理由があります。そのため、下記のような関わり方が必要となります。
噛まれた子どもが落ち着いたら、子ども同士でしっかりと仲直りをしましょう。噛んだ子どもに対しては、お友だちが痛かった事、跡が残ってしまった事を伝えて、ごめんねができるよう仲介します。
仲直りがしっかりできたあとは、まず噛んだ子どもに対して、噛んだ理由を聞きます。気持ちを認めて受け止めながらも、噛むという表現方法はいけないということをしっかり伝えます。その上で、噛む方法ではなく、言葉で自分の気持ちを伝える方法を示します。
例えば・・・
「おもちゃが取られそうになって、嫌だったんだね。それは嫌だったよね。集中して遊んでたもんね。でも噛んだらとっても痛いから、やめようね。次からお口で言ってみようね。なんて言えばいいかな?」と子どもの気持ちに共感しながら、問いかけるように話します。その後子どもから答えが出る事もありますが、なかなか難しいかと思いますので、「やめて!って言ってみよっか」などと提案していきます。
噛み付きという行為自体はしてはいけない事ですが、その奥にある気持ちに寄り添い、噛むのではなく、別の行動を伝えていく事が大切であり、噛み付き癖をなくす方法でもあります。
噛まれた子どもへの対応

噛まれてしまったら、まずは速やかに噛んだ子どもと引き離して、痛かった気持ちを受け止め、噛み跡を確認します。
適切な処置を行った後、噛んだ相手のごめんねの気持ちを聞き入れられるよう、仲介をしながら言葉掛けをします。
保護者への対応の仕方

上記の処置方法でもお話をしましたが、保育園の伝え方や対応によって保護者の方の受け取り方も大きく変わってきます。
噛んでしまった子どもの保護者に対しては、どんな状況で噛んでしまったのか、その後保育園ではどのような関わりをしたかを伝えて、ご家庭でも気持ちを受け止めてもらいながらも、気をつけて関わってもらえるように話します。
噛んだ相手の名前を伝える保育園もありますが、保護者同士のトラブルを防ぐため、あえて伝えない保育園もあるようです。噛まれてしまった子どもの保護者に対しては、まずは謝罪をした上で、詳しい状況をお伝えします。その上で、再発防止のための具体的な改善策をお伝えします。
保育園で噛み付きが起きてしまった際に大切な事は、保護者の方へ誠意を持って状況報告と謝罪をする事です。
噛み付きを防ぐために
保育園で保育士が行うべきこと
噛み付きは子ども同士が近くにいる時に起こりやすいです。子ども同士の距離が近い場合には、保育者が側について見守るようにしましょう。
朝や夕方の合同保育等どんな状況であっても止める事が出来るように、噛み付き癖がある子どもや可能性がある子どもなどの情報共有は保育園全体で行っていきます。
噛み付き癖がある子どもに関しては、保育者が1人側について見守るようにしている保育園もあります。
保育士同士言葉掛けをし合いながら、安全な保育環境を整えていきましょう。
ご家庭で親が行うべきこと
もし自分の子どもが保育園で友だちを噛んでしまったら、ご家庭でもお話をしてみましょう。
「今日保育園で噛んじゃったんだって?どうして嚙んじゃったのかな」と聞いてみると、子どもの理解や年齢、発達によって異なりますが、子どもの方からお話をしてくれるかもしれません。
その際は叱るのではなく、お話してくれたことに対してありがとうと伝えて、次からはしないこと、言葉で伝えることを伝えていきましょう。
お話をしてくれない場合、お話をすることが難しい年齢の場合でも、「アム(噛み付きの事)しちゃいけないよ」とお話ししましょう。
おすすめ転職サイト
保育園の人間関係でお困りではないですか?
でも保育士求人サイトってたくさんあって迷いますよね…。
そのような方に向けた、おすすめの保育士転職サイトをご紹介します。
保育バランス
残業が少なく、働きやすい職場が多数掲載されています。
事業所内保育所への転職を紹介してくれます。
少人数でゆったりと保育をしたい方、時間外労働はできるだけしたくない方、行事や書類仕事に追われるのが嫌な方にオススメです。
保育畑
最初の登録で、転職で重視したいポイントを入れるので、自分の希望した保育園が見つかりやすいです。
保育メトロ
上京して東京で働きたい方向けのサイトです。
上京と転職をサポートするサービスなので、不安が多い方も安心して転職することが出来ます。
レバウェル保育士
好条件・高収入の求人も多数掲載しています。
面接対策から条件交渉まで徹底サポートしてくれます。
保育求人ラボ
専任のアドバイザーがマンツーマンで保育士さんの就職・転職をサポートしてくれます。
保育園、幼稚園を初め児童発達支援や放課後等デイサービスなどの求人を多数掲載していて、独自の非公開求人が多いのもポイントです。
保育求人ラボ+(保育求人ラボ プラス)という保育系の管理職特化の紹介サービスも展開しています。
保育業界には珍しく、経験が長い先生向けのハイキャリア向けサービスも行っています。
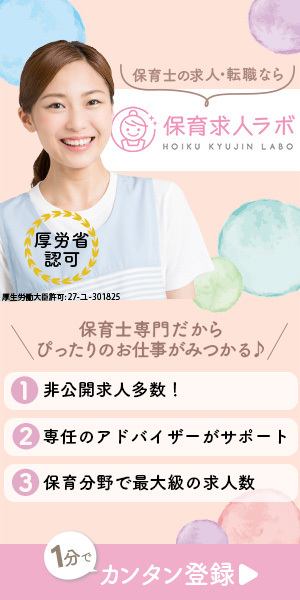
せんとなび
保育現場での実務経験があり、福祉の現場をよく知るコンサルタントが、あなたにマッチした職場を紹介してくれます。
仕事内容、待遇面、人間関係など聞きにくいこともコンサルタントに直接聞くことができるのもポイントです。

保育エイド
人間関係に悩んでいる方に向けた転職サイトです。
人間関係が良好で風通しの良い保育園の求人情報を多数掲載しています。
まとめ

噛み付きとは
◯自我の芽生えにより、自分の気持ちやしたい事が出てきたけれど、まだ自分の気持ちを言葉にして相手に伝えることが難しいため、噛み付きという行動が見られるようになる
◯成長の証でもあり、だれもが通る可能性がある発達段階
噛み付きの原因3選
〇理由なき噛み付き
そこに噛むものがあったから、理由がなく、噛んでみたかったから噛んでみた、という噛み付き
0.1歳児の低年齢の子どもに多く、保育園で子ども同士の距離が近い時に起こりやすい
指先を使って遊べるようなおもちゃのリモコンやシリコンプチプチ、歯固めなどを用いて、別の方法で遊びにつなげていくと良い
〇自分の気持ちを相手に伝えるための表現方法
自分の気持ちは明確に出てきたけれど、相手に言葉にして伝えるという事が咄嗟に出来ないときに見られる行動
2.3歳の子どもに多く見られる
子どもの気持ちを受け止めて言葉で代弁し、その後噛むことはいけない事だと伝え、別の方法で自分の気持ちを伝えられるよう示していく
一方的に叱るのはNG!
〇甘えたい気持ちの表れ
1歳前後に起こりやすく、慣れている保育士やパパママに噛むことが多く、甘えたい気持ちや遊んでいるつもりで噛むことがある
わかりやすい言葉で噛むことはいけないことだと伝えるようにする
甘えだから・痛くないから、と思ってスルーしたり遊んだりはNG!
保育園で噛み付きが起こったときの対処法
〇必要な処置
もし噛み付きが起こった場合には、まず流水で流して噛み跡の状態を確認する
赤く歯形に内出血の痕が残る、などの外傷がある場合は、冷やすと良いとされているが、保育園によって対応は異なるため、看護師や園長、園医の指示に従うように
出血があったり大きくあざになってしまっている場合は、速やかに保育園の看護師や園医に相談する
〇噛んだ子どもへの対応
0.1歳の低年齢児の子どもが噛んだ場合は、短い言葉で、「痛いよ。ブッブーだよ。」などと噛んだことはいけないことを伝える。一度で理解することは難しいため、噛みつこうとする様子が見られた場合には素早く止めた上で、繰り返しわかりやすく言葉や表情で伝えていく
2.3歳の場合は、噛んだ理由があることがほとんどであるため、子ども同士でしっかりと仲直りをした後、噛んだ子どもに対して、噛んだ理由を聞き、気持ちを認めて受け止める。その後噛む方法ではなく、言葉で自分の気持ちを伝える方法を示していく
〇噛まれた子どもへの対応
速やかに噛んだ子どもと引き離して、痛かった気持ちを受け止め、噛み跡を確認する
適切な処置を行った後、噛んだ相手のごめんねの気持ちを聞き入れられるよう、仲介をしながら言葉掛けをする
〇保護者への対応の仕方
噛まれてしまった子どもの保護者に対しては、まずは謝罪をした上で、詳しい状況をお伝えし、再発防止のための具体的な改善策を伝える
※保育園で噛み付きが起きてしまった際に大切なことは、保護者の方へ誠意を持って状況報告と謝罪をすること
噛み付きは、発達段階で見られる行動の一つであり、成長の証でもあります。
ですが、保育園は大切な子どもの命を預かっている以上、噛み付きは未然に防がなくではいけません。保育士同士で言葉かけをし合いながら、安全な環境を作っていきましょう。

子どもに対しては、噛み付きという行為自体はしてはいけないということを伝えた上で、その奥にある気持ちに寄り添い、噛むのではなく、別の行動を伝えていくことが大切です。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。




